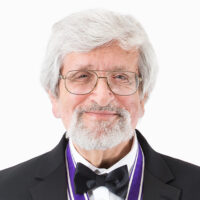
Richard Taruskin
第33回(2017)受賞
音楽
/ 音楽学者
1945 - 2022
カリフォルニア大学バークレー校 名誉教授
従来の歴史記述の方法を乗り越えた斬新な音楽史研究と、該博な知識に裏打ちされた先鋭的な批評によって、西洋の音楽文化に新たな次元を切り拓いてきた。他の追随を許さないその仕事は、音楽において言論が創造的価値を持つことを示し、音楽の世界に大きな足跡を残した。
リチャード・タラスキン博士は、古楽の演奏、研究から出発し、近代ロシア音楽に関する画期的かつ重要な研究を行い、さらに大部の西洋音楽史を発表して、読者を啓発し続けてきた音楽学者、批評家である。
コロンビア大学でロシア語を、そして大学院では西洋音楽史を中心に音楽学を専攻し、歴史的音楽学で博士号を取得後、同大学に奉職した。1980年代を中心に『ニューヨーク・タイムズ』紙をはじめとする新聞や論文などで展開した主張は、同時代の古楽演奏が、しばしばその拠り所とする「真正性(オーセンティシティー)」にではなく、むしろ20世紀後半の美学を反映しているという刺激的な立論で、それは、その後の古楽演奏に有形無形の影響を及ぼし、現代に到っている。
ロシア音楽研究においても強い影響力を持っている。ロシアのオペラや、作曲家のムソルグスキー、ストラヴィンスキーなどについての研究は、民俗学をはじめとする周辺情報を徹底的に渉猟しながら、作品自体にも深く斬りこむ画期的な手法によって作曲家像を塗り替え、音楽学研究の方法論自体を更新した。
また、6巻からなる『オックスフォード西洋音楽史』(2005)は、記譜(書記性)によって伝承された音楽という独自の視点によって貫かれており、一人の著者によって書かれた最大の音楽通史として、21世紀の音楽学における金字塔である。タラスキン博士は、これまで同質的な基準の下で書かれてきた西洋音楽の歴史が、その実、互いに異質で微細な歴史の集合体として成り立っていることを、実際の膨大な記述によって示そうとした。そこには、民族音楽学の方法論上の成果や、歴史記述に対する歴史学の批判的取り組みからの影響も読み取れる。音楽以外の多様な文化領域についての深い考察を駆使しながら、それを記譜された音楽の分析とより合わせていく斬新な西洋音楽学史の記述はスリリングかつ啓発的である。
タラスキン博士は、音楽に関する従来の批評と学問との境目を取り払い、また伝統的な音楽史学と民族音楽学との境目を取り払うという新たな次元を音楽研究に切り拓いた。音楽において、作曲や演奏だけではなく、緻密なことばを通して文脈化する作業がきわめて創造的であり、世界の音楽文化に貢献するものであるということを、きわめて高い次元で示した。
以上の理由によって、リチャード・タラスキン博士に思想・芸術部門における第33回(2017)京都賞を贈呈する。
プロフィールは受賞時のものです