
Isamu Akasaki
第25回(2009)受賞
エレクトロニクス
/ 半導体科学者
1929 - 2021
名古屋大学 特別教授、名城大学 教授
青色発光ダイオードの実現に向けて、永年にわたり粘り強く研究を進め、ほぼ不可能と思われていた窒化ガリウム系pn接合を実現する先駆的な成果を世界に示した。この成果は、青色発光素子の実用化に向けての力強い一歩となった。同氏はその後も先導的に研究を進め、その貢献は世界的に高く評価されている。
赤﨑勇博士は、青色発光ダイオードの実現に向け、永年にわたり窒化ガリウム(GaN)結晶の成長と素子応用の研究を粘り強く進め、ほぼ不可能と思われていたGaN系pn接合を実現する先駆的な成果を達成した。この成果は、内外の研究の流れを変え、青色発光素子の実用化に向けた研究を活性化させる歴史的一歩となった。同氏は、その後も先導的研究を一貫して進めており、その貢献は世界的に高く評価されている。
半導体を用いた発光ダイオード(LED)は、効率や寿命などに優れ、多様な応用がある。このため早くから研究開発が進み、赤色や緑色の発光素子などが実現されてきた。さらに、青色LEDが実現すれば、光の3原色が揃い、フルカラーの表示や白色照明などへと応用が拡がるものと期待されていた。また、青色の半導体レーザが実現できれば、光ディスクの記録密度を格段に高められることなどが予測されていた。このため、青色LEDを目指す試みが1970年頃から活発になり、有望な材料としてGaNが注目され、精力的な研究が推進された。しかし、GaN結晶の質を高め、電気的性質を制御することは難しく、n型結晶は実現されたが、LEDに不可欠のp型結晶は実現できなかった。このため、70年代末には、研究者の多くがGaN系青色LEDの実現を断念し、撤退した。
しかし、赤﨑博士は粘り強く研究を続け、1985年には、サファイア基板に低温で緩衝層を形成した後にGaNを成長すると、品質が格段に高まることを見出した。さらに、質の高まったGaN結晶にマグネシウム原子を導入し、電子線を照射すると、結晶がp型化することを、天野浩博士らの協力を得て、発見した。続いて、この手法により世界初のGaNのpn接合を1989年に実現し、青色LEDとして動作することも示した。
これらの成果は、青色発光素子材料としてのGaN系材料の可能性を再認識させ、実用化に向けた研究開発が内外で精力的に推進される引き金となった。この結果、関連の研究が進み、青色LEDが1993年に実用化され、今では表示と照明に広く用いられている。また、青色半導体レーザも、その後に実用化され、高密度光記録機器の実現などに重要な役割を果たしている。赤﨑博士は、こうした青色発光素子の実現への道を拓くとともに、一連の研究を通じ、その後の発展にも先導的な貢献をなした。
以上の理由によって、赤﨑勇博士に先端技術部門における第25回(2009)京都賞を贈呈する。
プロフィールは受賞時のものです

青色LEDの発明に貢献、赤﨑勇博士を偲ぶ
青色発光ダイオード(LED)の発明に貢献した赤﨑勇博士が4月1日、逝去されました。92歳でした。 赤﨑博士は、窒化ガリウム(GaN)の結晶成長と発光ダイオードへの応用の研究を粘り強く進め、青色発光ダイオードの発明への道を...

赤﨑勇博士が「エリザベス女王工学賞」に輝く!
2009年に京都賞先端技術部門を受賞した赤﨑勇博士が2月2日、技術革新によって世界に恩恵をもたらした研究者を表彰する「エリザベス女王工学賞」の受賞者に選ばれました。このたびのご栄誉、誠におめでとうございます! 赤﨑博士は...
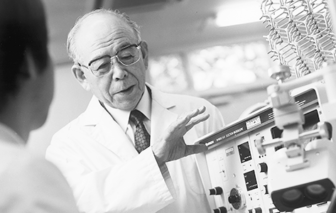
赤﨑博士がノーベル物理学賞を受賞
10月7日、ノーベル物理学賞の受賞者発表が行われ、第25回(2009)京都賞 先端技術部門受賞者の赤﨑勇博士が選ばれました。授賞式は12月10日、スウエーデンのストックホルムで行われます。